
畑が荒らされ、収穫目前の作物が台無しに …そんな悔しい思いをしていませんか?北海道ではエゾシカやカラスによる農業被害が深刻化しており、農家の方々にとって「有害鳥獣駆除」は他人事ではありません。
この記事では、有害鳥獣駆除の基本的な仕組みから申請方法、地域の取り組み事例までを解説します。「誰かがやってくれる」ではなく、「自分も関わる」ための第一歩として、ぜひご活用ください。
有害鳥獣駆除とは何か?

有害鳥獣駆除の定義・目的と法的な制度の概要について解説します。農業を守るための制度的な枠組みを理解することで、駆除活動への第一歩が踏み出しやすくなります。
- 定義と目的
- 法的根拠と制度概要
定義と目的
「有害鳥獣駆除」とは、農作物や生活環境に被害を及ぼす野生動物を、法律に基づいて捕獲・排除する取り組みです。目的は単なる動物の排除ではなく、農業の継続、地域の安全、生態系のバランスを守ることにあります。
特にシカやカラス、またはイノシシやクマによる被害が多く、放置すれば収穫量の減少や農地の荒廃につながる恐れがあります。
法的根拠と制度概要
駆除は「鳥獣保護管理法」に基づいて行われます。通常の狩猟とは異なり、狩猟期間外でも行政の許可を得て駆除が可能です。
鳥獣保護管理法の目的は、以下のように記されています。
この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
参照:e-Gov法令検索
市町村が主体となり、猟友会や地域住民と連携して実施されるケースが多く、国などからの補助金制度も整備されています。
2025年9月1日:改正鳥獣保護管理法
また、2025年9月1日には「改正鳥獣保護管理法」が新たに施行されます。
改正前は住宅が密集している市街地で猟銃を使用することは禁止されており、これまで市街地にクマが出没したケースでは人に危険が生じている場合に限り警察官が別の法律に基づいて発砲を命じるなどしていました。
しかし、市街地へのクマの出没が相次ぐ中、市町村の判断で特例的に猟銃の使用を可能とすることなどを盛り込んだ改正鳥獣保護管理法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
現在は改正に向けて各都道府県と市区町村で連携をしながら発砲から捕獲までの一連の手順を確認する訓練も行われています。
対象となる有害鳥獣の種類

北海道を中心に、農業被害の原因となる鳥獣の種類と地域ごとの重点対策動物を解説します。自分の地域ではどの動物が問題視されているか考えていきましょう。
地域ごとの重点鳥獣
ここでは北海道を例にして以下の鳥獣が重点的に駆除対象とされています。
| 鳥獣名 | 主な被害内容 |
|---|---|
| エゾシカ | 畑の作物を食害、柵の破壊 |
| カラス | 種まき直後の種子を掘り返す、果樹の食害 |
| ヒグマ | 人身被害の恐れ、養蜂・畜産への被害 |
| キツネ・タヌキ | 鶏舎への侵入、病原菌の媒介 |
▶関連記事「【狩猟動物】代表的な10種とおすすめの狩猟方法を銃砲店が解説」
有害鳥獣駆除の申請方法と手続き

ここでは駆除を依頼・実施するための具体的な方法を紹介や、誰が申請できるのか、どんな流れで進めるのか、必要な資格は何かについて解説します。
- 誰が申請できるのか?
- 申請の流れ
- 必要な資格・免許
誰が申請できるのか?
申請できるのは以下のような方です。
- 農業者本人(被害を受けている方)
- 地域の猟友会や狩猟者
- 自治体(市町村)
- 鳥獣被害対策実施隊(地域で組織された専門チーム)
農家の方が直接申請することも可能ですが、猟友会や自治体と連携することでスムーズに進められます。
申請の流れ
- 市町村の農政課・環境課に相談 被害状況の報告(写真・被害面積など)
- 駆除計画の提出(対象動物・方法・期間など)
- 許可証の発行(狩猟免許保持者に限る)
- 駆除の実施と報告(捕獲数・場所など)
自治体によって様式や必要書類が異なるため、まずは地元の役場に問い合わせるのが確実です。
必要な資格・免許
駆除を実施するには、以下の狩猟免許が必要です。
| 免許の種類 | 対象猟法 | 初心者向け |
|---|---|---|
| 第一種銃猟 | 散弾銃・ライフル | 銃所持許可が必要 |
| 第二種銃猟 | 空気銃 | 比較的取得しやすい |
| 網猟又はわな猟 | むそう網・箱罠など | 初心者におすすめ |
「自分で駆除したい」と考えている方は、まず「網猟又はわな猟」の取得を検討してみましょう。講習会や試験は年に数回開催されています。
▶関連記事「網猟免許の取り方を解説!試験のポイントと問題例を押さえて合格率アップ!」
▶関連記事「【罠猟とは?】罠の種類・ポイント・必要な免許と試験の概要を解説!【罠猟経験者が語る】」
【地域別】有害鳥獣駆除の取り組み事例

ここでは、北海道内でおこなわれている地域ぐるみの取り組み事例を紹介します。駆除は個人の努力だけでなく、地域全体の協力が成果につながることがわかります。
① 北海道標茶町(しべちゃちょう)
対象鳥獣:エゾシカ
背景:エゾシカによる農作物被害が深刻化。個体数の増加とともに、牧草地や畑への侵入が頻発していた。
取組内容:
- 地元猟友会と連携し、捕獲活動を強化。
- 電気柵の設置支援と、地域住民への設置講習会を実施。
- GPS付発信機を用いた行動追跡により、出没エリアの可視化。
成果:
- 被害面積の減少。
- 若手猟師の育成にもつながり、地域の担い手確保に貢献。
② 北海道中川町
対象鳥獣:カラス・エゾシカ
背景:カラスによるトウモロコシ被害、エゾシカによる牧草地の食害が問題化。
取組内容:
- 地域住民が「鳥獣対策協議会」を設立。
- カラス対策として、レーザー照射装置や音響機器を導入。
- エゾシカ対策では、広域電気柵の共同設置と定期的な見回りを実施する。
成果:
- 被害額の大幅減少。
- 地域住民の防除意識が向上し、継続的な活動が定着した。
③ 北海道厚岸町(あっけしちょう)
対象鳥獣:エゾシカ・キツネ
背景:エゾシカによる牧草地の踏み荒らし、キツネによる家畜感染症リスク。
取組内容:
- 地域ぐるみで「鳥獣害対策マップ」を作成し、出没情報を共有。
- 小中学校での環境教育を通じて、次世代への意識啓発。
成果:
- 家畜の感染症リスクが低下。
- 地域の防除活動が教育と連動し、持続可能な仕組みへ。
これらの事例では、地域住民の協力体制や情報共有が成果につながっています。「自分も関わりたい」と思ったら、まずは地域の猟友会や自治体に相談してみましょう。
まとめ
有害鳥獣駆除は、農業を守るための大切な取り組みです。制度や申請方法を知ることで、「誰かがやってくれる」から「自分も関わる」へと意識が変わります。
農家の皆さんにとって、有害鳥獣の被害は日常の課題。まずは地元の役場や猟友会に相談し、地域の取り組みに参加することで、農地を守る力になります。「駆除=排除」ではなく、「地域を守る活動」として、ぜひ一歩踏み出してみてください。
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。




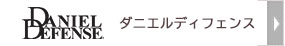





















コメントを残す