
銃のトリガー(引き金)は、発射の瞬間を制御する極めて重要な構造です。トリガーの種類や作動方式によって、操作性・命中精度・安全性が大きく変わります。
本記事では、日本の猟銃に焦点を当て、トリガーの基本構造から、銃種によるシステムの違い、そして最も重要な安全な取り扱いのポイントまでを、分かりやすく解説します。
実用的な視点でトリガー選びをサポートする内容となっていますので、銃器の理解を深めたい方、これから銃を選ぶ方はぜひ参考にしてください。
銃のトリガーとは?基本構造と役割を理解しよう
トリガーは、射手が指で操作し、内部の撃発機構を作動させて弾丸を発射させるための引き金です。トリガーを引くと、シアー(逆鉤)と呼ばれる部品が外れ、ハンマーまたはストライカーが解放されます。その力がファイアリングピン(撃針)に伝わり、弾薬の雷管を叩くことで発射に至ります。この一連の動作が、銃の基本的な発射メカニズムです。
ハンマー式とストライカー式の違い
主にボルトアクションライフルなどで見られる違いです。
ハンマー式
ハンマー(撃鉄)がファイアリングピンを叩く構造。
ストライカー式
ハンマーを持たず、スプリングの力で圧縮されたストライカー(撃針そのもの、または撃針と一体化した部品)が直接前進して雷管を叩く構造。部品点数が少なく、ロックタイム(トリガーを引いてから発射されるまでの時間)が短い傾向があります。
それぞれに操作感や安全性の違いがあり、用途や好みに応じて選ばれます。
猟銃におけるトリガーシステム

猟銃を選ぶ際、トリガーシステムを単体で自由に選べる機会は極めて限定的です。多くの場合、ボルトアクション、上下二連、自動銃といった銃の形式を選ぶと、それに搭載されているトリガーシステムも必然的に決まります。 したがって、「用途別にトリガーを選ぶ」というよりは、「選んだ銃のトリガー特性を深く理解し、使いこなす」という考え方が現実的です。
ボルトアクションライフルのトリガー
精密射撃で使われることが多いため、トリガーの「切れ味」が重視されます。
ダイレクトトリガー:引いていくと、ある点で突然シアーが外れる単一段階のトリガー。
ツーステージトリガー:引き始めに少し遊び(第一段階)があり、重くなった点(第二段階)からさらに少し引くと発射される二段階のトリガー。発射のタイミングが予測しやすいため、精密射撃に向いているとされます。
散弾銃のトリガー
上下二連銃や自動銃など、形式によって構造が異なります。特に、速射性が求められる場面で使われることが多いため、操作の確実性が重視されます。
トリガープル(引きの重さ)と操作性
トリガープルとは、トリガーを引くのに必要な力のことです。
軽いトリガープル:指の動きによる銃のブレを最小限に抑えられるため、精密な射撃では有利に働きます。しかし、意図せず触れただけで発射してしまう「暴発」のリスクも高まります。
重いトリガープル:意図しない発射を防ぎやすく安全性は高いですが、引き絞る際に銃がブレやすく、特に精密射撃では不利になることがあります。
銃を選ぶ際には、実際に構えてみて、そのトリガーの重さや「切れの良さ」(遊びが少なく、スパッとシアーが切れる感覚)を確認することが非常に重要です。
安全に扱うために知っておきたいポイント

銃の安全な取り扱いにおいて、トリガーの構造理解以上に重要なのが、日本の法律の遵守と、それに伴う安全装置の正しい認識です。
発射の時機が到来するまでは装填しない
日本の銃刀法では大原則として「発射の時機が到来するまでは弾丸を装てんしないこと」と定められています。これは、猟場であっても、獲物を見つけ、狙いを定め、まさに「今撃つ」という瞬間まで、薬室に弾を装填してはならないということです。したがって、安全装置をかけた状態で装填したまま移動・待機することは、法律の趣旨に反する極めて危険な行為です。
安全装置(セーフティ)の役割と構造的限界
上記の大原則から言えば、日本の法律を遵守する限り、安全装置は本来不要とさえ言えます。しかし、多くの猟銃には安全装置が装備されています。その役割と限界を正しく理解する必要があります。
構造について
多くの猟銃の安全装置は、単にトリガーの物理的な動きをロックしているだけとなっています。シアーやハンマーといった内部の撃発機構そのものを完全に固定する構造にはなっていません。
危険性について
万が一装填している状態で安全装置をかけていても、銃に強い衝撃(転倒して岩にぶつけるなど)が加わると、シアーが外れて激発し、暴発に至る危険性があります。 安全装置は絶対的な安全を保証するものではなく、過信は絶対に禁物です。
トリガーのメンテナンスと改造に関する注意点
トリガー周辺は、汚れや摩耗によって作動不良や誤作動を起こす可能性があります。定期的な清掃と、必要に応じた調整が安全運用の鍵です。
メンテナンス
トリガー周辺の機構部にゴミや汚れが溜まると、作動不良や思わぬ誤作動の原因となります。定期的な清掃と、可動部への適切な注油を心がけてください。
改造の禁止
トリガープルを極端に軽くする、遊びをなくすといった調整や、社外品のトリガーへの交換は、銃刀法における「構造の変更」とみなされ、所持許可の取り消しや罰則の対象となる可能性があります。安易な改造は銃の安全性を著しく損なうため、絶対に行わないでください。調整が必要な場合は、必ず許可を持つ専門店に相談してください。
まとめ
猟銃のトリガーは、銃のモデルと一体であり、ユーザーが自由に選べる部分は多くありません。重要なのは、ご自身の愛銃が持つトリガーの重さ、切れ味、感触といった特性を深く理解し、それに習熟することです。
そして、何よりも優先されるべきは、日本の法律に基づいた安全な取り扱いです。「撃つ瞬間まで装填しない」という大原則を徹底し、安全装置の構造的な限界を認識した上で、それを過信しないこと。これが、日本で銃を扱う者にとっての絶対的な責務です。
狩猟に関するご相談は、ぜひシューティングサプライにお任せください。あなたの狩猟ライフをサポートするため、専門知識を持ったスタッフが丁寧にご案内します。
▶︎関連記事「銃のマガジン構造をわかりやすく解説|種類・仕組み・選び方の判断基準とは」
▶︎関連記事「銃のバレル構造をわかりやすく解説|種類・仕組み・選び方の判断基準とは」
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。




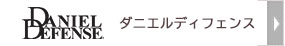





















コメントを残す