近年、日本の森林や農地で深刻化するニホンジカの増加問題。この現状に対し、鹿猟は単なる野生動物の捕獲を超え、生態系保護と資源の有効活用という重要な役割を担っています。
しかし、鹿猟には専門知識と深い理解が不可欠です。この記事では、鹿猟の意義からニホンジカの現状、具体的な狩猟方法、そして狩猟後の適切な処理までを詳しく解説します。
日本の豊かな自然と共生しながら責任ある狩猟を行うための、実践的な情報を提供します。
鹿猟の始め方はYouTubeでも解説!
「鹿猟」とは
「鹿猟」(しかりょう、または、ししがり)とは、日本においてニホンジカ(その亜種であるエゾシカ等も含む)を対象として行う狩猟活動を指します。
単に野生動物を捕獲する行為だけでなく、現代においては複数の重要な側面を持つ活動として位置づけられています。
まず、鹿猟の根底には、鳥獣保護管理法に基づく適正な個体数管理という目的があります。
近年、全国的にニホンジカの生息数が急増し、森林の若齢木や下層植生の食害による生態系の破壊、農林水産業への深刻な被害、さらには人身被害や交通事故の増加といった問題が顕在化しています。
鹿猟は、これらの被害を軽減し、健全な自然環境を維持するための有効な手段として実施されています。
また、鹿猟は捕獲した命を無駄にしない「命をいただく」という倫理観に基づいています。
捕獲されたシカは、ジビエ(野生鳥獣の肉)として食肉利用されるほか、角や皮なども資源として活用されます。これは、持続可能な資源利用の一環であり、食料自給率の向上や地域活性化にも貢献する可能性を秘めています。
鹿猟は、銃猟(巻き狩り、忍び猟、待ち伏せ猟など)やわな猟(くくりわな、はこわななど)といった多様な方法で実施されますが、いずれも専門的な知識、技術、そして厳格な安全管理が求められます。
法規制の遵守はもちろんのこと、周辺住民への配慮や、自然環境への敬意を持つことが、鹿猟を行う者に課せられた重要な責任と言えるでしょう。
ニホンジカの特徴と生息環境
日本には主に「ニホンジカ」が生息しています。地域によって以下のような亜種がいることが特徴です。
| 地域名 | 亜種名 |
| 北海道 | エゾシカ |
| 本州 | ホンシュウジカ |
| 四国・九州 | キュウシュウジカ |
| 対馬、長崎県の島しょ部 | ツシマジカ |
| 馬毛島、鹿児島県 | マゲジカ |
| 屋久島、鹿児島県 | ヤクシカ |
| 慶良間諸島、沖縄県 | ケラマジカ |
また、和歌山県では外来種であるタイワンジカの分布も確認されています。多くの鹿に共通していることですが、ニホンジカもオスにのみ角があり、全長は90〜190cm、体重は50〜130kgと個体差があります。
ニホンジカという名前が付けられていますが、日本固有の動物ではなく、東南アジアや中国の日本海側にも生息しています。
国内では奈良の鹿が有名ですが、実は奈良公園の鹿は1,000年以上前から日本人により守られてきたことが調査によって明らかになりました。
全国的に見ても非常に多くの個体が生息しており、増えすぎたため平成25年には「抜本的な鳥獣捕獲強化対策(環境庁、農林水産省)」の対象となり、ニホンジカとイノシシの個体数を10年(令和5年度まで)で半減させる計画が立てられました。
イノシシについては順調に進んだものの、ニホンジカについてはまだまだ個体数が多く、令和10年度まで期間が延長されています。
ニホンジカは特に若葉、樹皮、草本類などを食料とします。近年は、人里近くの農耕地にも出没し、農作物への食害が深刻化しています。
シカの被害について
シカは日本の在来種であり、全国的に分布を拡大し個体数が増加しています。このシカの増加は、全国で生態系や農林業に深刻な被害をもたらしています。
具体的な被害例(参考「狩猟ポータル」):
| 植生への影響 | シカは植物を食べるため、高山植物などへの影響が深刻です。植物がほとんどなくなったと考えられる林内の様子も報告されています。 |
| 森林の衰退 | 樹皮を食べられた木々が枯れ、森林が衰退する例も見られます。特に、樹幹を一周剥がされると木は枯れてしまいます。 |
| 生物多様性への影響 | 森林をはじめとする植生への影響が深刻な地域は、尾瀬や南アルプスなど、日本の生物多様性の屋台骨である国立公園にも及んでいます。森林が衰退することで、そこをすみかとする多くの動植物にも影響を与えます。 |
鹿猟の目的:個体数管理と資源の有効活用
鹿猟の主な目的は、以下の二点に集約されます。
個体数管理
シカの過剰な増加は、森林の下層植生の消失や稚樹の食害による森林の荒廃、農作物への深刻な被害、さらには交通事故の増加など、多岐にわたる問題を引き起こします。鹿猟は、これらの被害を軽減し、健全な生態系を維持するための重要な手段として位置づけられています。
資源の有効活用(ジビエ利用)
捕獲されたシカは、良質な食肉(ジビエ)として活用されるほか、角や皮なども利用されます。これは、命を無駄にしないという狩猟本来の精神に基づくものであり、持続可能な資源利用の一環としても注目されています。
鹿猟の方法:現場のプロが教える流し猟の基本とコツ
鹿猟には様々な方法がありますが、今回は「流し猟」を中心に、その準備から現場でのノウハウまでを解説します。
①鹿猟の準備:道具と車両の最適化
鹿猟を始める前に、適切な準備が不可欠です。
- 道具
鹿を仕留めるための銃(散弾銃やライフル銃)は当然として、狩猟後の作業を考慮した道具も重要です。100kgを超えるシカを運搬・解体するためには、切れ味の良いナイフやノコギリ、運搬用のロープやシャックル、カラビナがあると非常に便利です。特に荷台がない車での猟では、その場での解体が必須となるため、適切な解体用具の用意が必須です。
- 車両
流し猟では、林道など未舗装路を走行することが多いため、軽トラックやピックアップトラックなど、荷台がある車が便利です。車高を上げておくことで車下部のヒットを防ぎ、ウィンチを装備すれば、一人でも大型のシカを積み込む際の労力を大幅に軽減できます。国有林・道(県)有林への侵入には、必ず許可証を提示する必要があります。
②現場で役立つ「鹿撃ち」のコツ
経験豊富なハンターのノウハウは、猟の成功率を大きく左右します。
- 時期選び
木の葉が落ちた時期がおすすめです。特に12月の降雪前や降雪後であれば、視界が良好で、シカの足跡や体色も雪上で見つけやすくなります。ただし、シカからも発見されやすい点に注意が必要です。
- シカの発見
林の中の「違和感」を見逃さないことが重要です。見慣れた猟場であれば、わずかな草の揺れや、普段ない木の影などに気づけるようになります。定期的に同じ猟場に通うことで、その地の特性を把握し、経験を積むことが成功への近道です。
- 射撃の精度
シカを撃つ際は、依託(いちゃく)可能な場所を探しましょう。太い木の枝や盛り上がった土、あるいはリュックなどを利用して銃を安定させることで、反動やブレを抑え、命中率を大幅に向上させることができます。
③捕獲後の流れと安全管理
シカを仕留めた後も、ハンターとしての責任は続きます。
- 処理方法
捕獲したシカは、業者に引き渡すか、自分で解体するかのいずれかになります。業者引き渡しの場合、着弾部位や健康状態、迅速な放血、納入までの時間制限など厳格な条件があります。自分で解体する場合は、その場で迅速に処理を行う知識と、専用のナイフ、衛生的な服装が不可欠です。残滓は全て持ち帰るのが原則です。
▶おすすめ資料「エゾシカ利活用のための捕獲・運搬テキスト」
- 流し猟時の注意点
道路上での銃カバーの確実な着脱は法律で義務付けられており、周囲への配慮も重要です。林道内では、対向車や動物との接触を避けるため、常に徐行し、すぐに停止できる速度を保ちましょう。
- 射撃時の安全
発砲前には、周囲の安全確認(人、民家、バックストップとなる地形など)を徹底します。法面(道路の斜面)は道路扱いのため、銃カバーを外して発砲できない点にも注意が必要です。
- 半矢の対処
シカが半矢(致命傷を負いながらも逃げ出した状態)となった場合は、基本的には銃で確実に止め刺しを行いましょう。特に大型のオスジカは、負傷した際に攻撃的になる可能性があり、ハンター自身の安全を最優先することが重要です。
まとめ
この記事では、「鹿猟」の定義から始まり、ニホンジカの生態や個体数増加による深刻な被害、そして個体数管理とジビエ利用という鹿猟の二つの大きな目的について深く掘り下げました。
さらに、銃猟やわな猟といった具体的な狩猟方法に加え、狩猟前の準備から現場でのコツ、そして捕獲後の適切な処理と安全管理まで、実践的なノウハウを網羅的に解説しています。鹿猟は、自然との共生を考える上で欠かせない、責任と倫理が求められる活動です。
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。


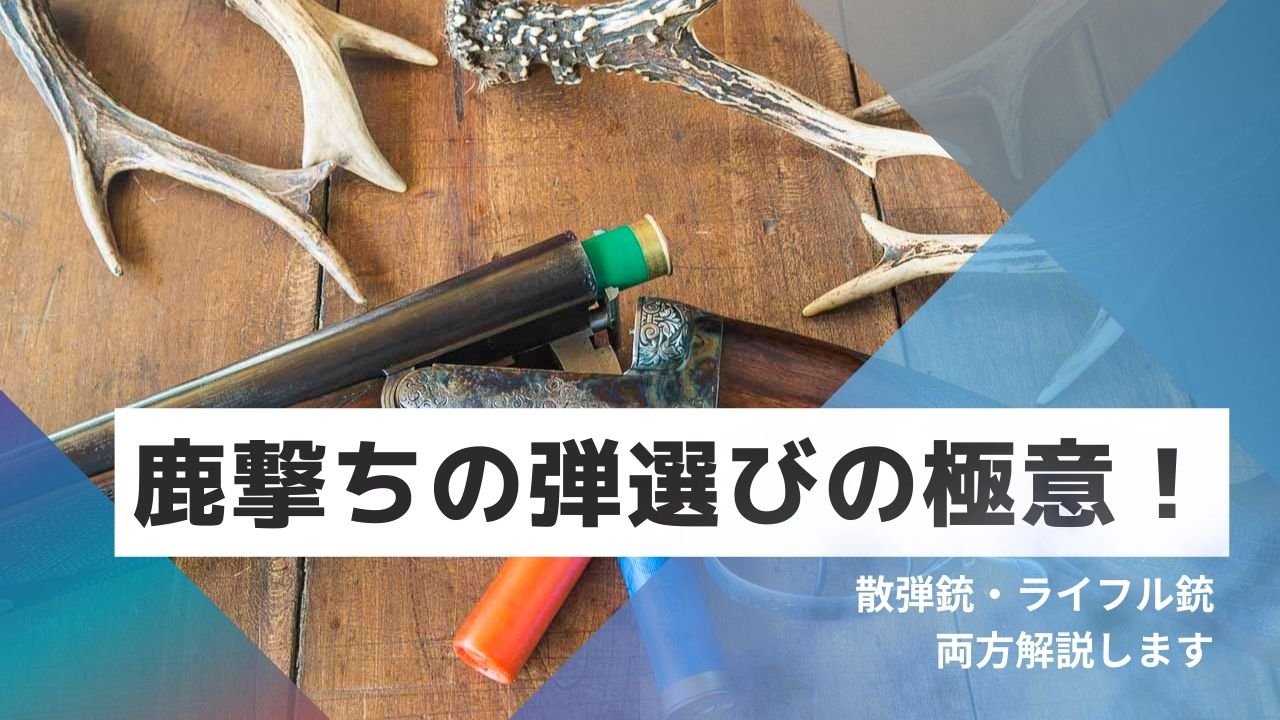
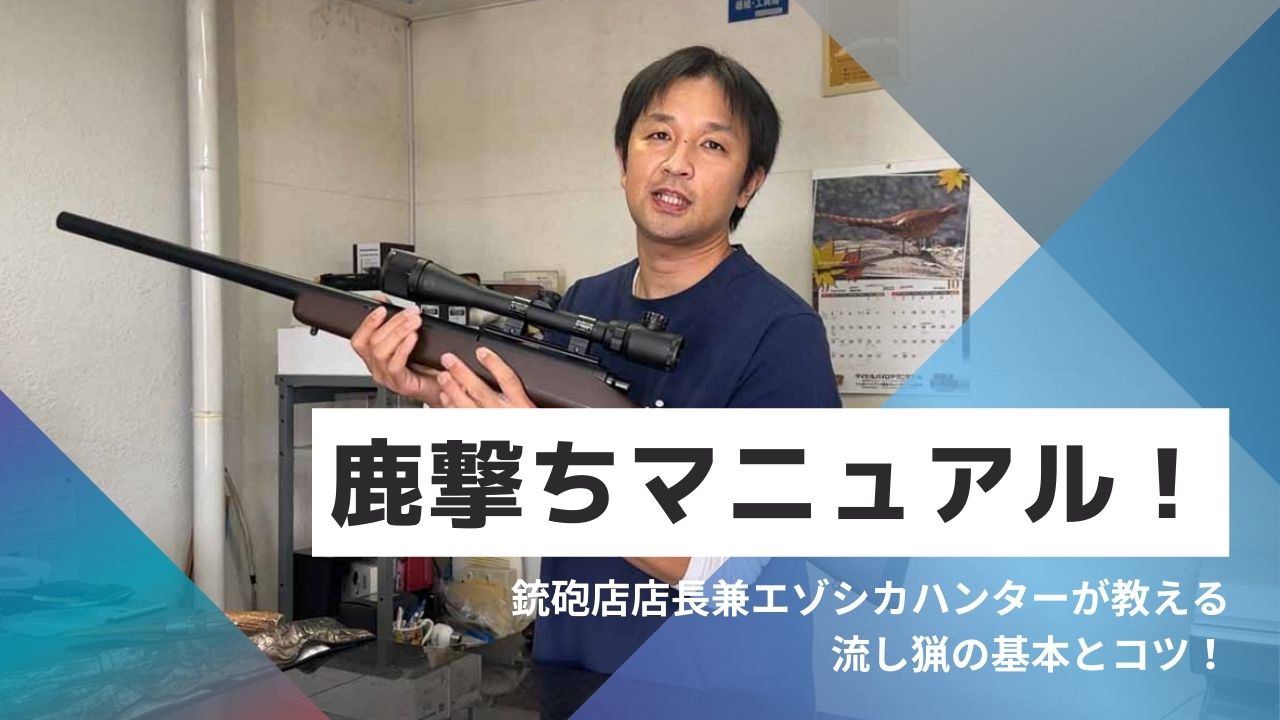




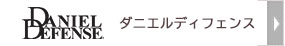





















コメントを残す