キジバトは、日本の里山から市街地、公園に至るまで幅広く生息する、私たちにとって非常に身近な鳥です。
その姿や「デデッポッポー」という特徴的な鳴き声は多くの人に親しまれていますが、実は狩猟鳥獣の一種として、適切な管理のもと狩猟が許可されています。
キジバトとは?その特徴と生息環境
キジバトは、ハト目ハト科に分類される鳥類で、その名の通りキジのような美しい斑紋が特徴です。
全長約33cmで、全体的に茶褐色をしており、首の側面には黒と淡褐色の特徴的な横縞模様があります。
日本全国に分布する留鳥ですが、雪深い地域では冬に暖かい場所へ移動する漂鳥としての性質も持ち合わせています。
主に平地から山地の森林、農耕地、河川敷に生息しますが、近年は都市部の公園や庭先でもよく見られるようになりました。植物食で、穀物や豆類、果実などを好んで食べます。
キジバトが狩猟対象となる理由
キジバトは、鳥獣保護管理法によって定められた狩猟鳥獣26種の一つです。
狩猟鳥獣は、個体数が安定しており、狩猟によってその種が絶滅する恐れがないと判断された動物です。キジバトは繁殖力が強く、安定した個体数を維持しているため、狩猟による資源利用が認められています。
また、農耕地や果樹園での食害が報告されることもあり、個体数調整の一環として狩猟が行われる側面もあります。
ただし、1日あたりの捕獲制限は10羽までと定められています。これは、無秩序な乱獲を防ぎ、持続可能な狩猟を確保するための重要なルールです。
キジバトは意外に美味しい?
適切な狩猟免許を持ち、定められた猟期や捕獲制限(1日10羽まで)などのルールを守れば、合法的に捕獲し、食用とすることが認められています。
実際に、キジバトの肉は「ジビエ」として古くから利用されており、その風味豊かな味わいは、多くの狩猟愛好家や料理人によって高く評価されています(参考記事はこちら)。
キジバト狩猟の主な方法
キジバトの狩猟には、主に銃猟が用いられます。
1. 銃猟(散弾銃)
散弾銃による狩猟は、飛び立つキジバトを狙い撃つのが一般的です。
- 待ち伏せ猟
キジバトが餌を求めて集まる農耕地、果樹園、または水場などで、ハンターが隠れて待ち伏せる方法です。早朝や夕方など、鳥の活動が活発な時間帯が狙い目となります。
- 忍び猟
キジバトがよく利用する木々や電線などに止まっているところを、音を立てずに接近して狙う方法です。警戒心の強い鳥なので、いかに気づかれずに近づけるかが重要になります。
- デコイ(鳥の模型)の使用
キジバトの群れは、仲間の近くに降り立つ習性があります。そのため、地面や木の枝にデコイを設置して、キジバトを誘き寄せる方法も効果的です。視覚的に群れがいると認識させることで、警戒心を和らげ、接近しやすくします。
- 見つけ方のコツ
狩猟経験者からは、「遠くからキジバトが飛んでくる方向を常に意識すること」や、「電線に止まっている鳥は意外と見落としやすいので注意すること」などのアドバイスがあります。キジバトは一度飛び立っても、近くの木などにすぐに止まる習性があるため、どこに降りたかを見極めることも大切です。
2. 網猟(なげ網)
一部地域では、手投げ網(なげ網)による捕獲も行われますが、こちらは高い技術と経験を要します。近距離から正確に網を投げかけ、鳥を絡め捕る方法です。
捕獲後の処理と注意点
捕獲したキジバトは、食肉として利用できます。ジビエ肉として美味しくいただくためには、適切な処理が不可欠です。
- 迅速な血抜きと内臓処理
捕獲後すぐに血抜きを行い、内臓を取り除くことで、肉の鮮度を保ち、臭みを抑えることができます。
- 十分な加熱
キジバトの肉は、他のジビエ肉と同様に、E型肝炎ウイルスや寄生虫のリスクを考慮し、必ず中心部まで十分に加熱して食べましょう。生食や半生は絶対に避けてください。
- 衛生管理
調理器具の洗浄・消毒も徹底し、食中毒のリスクを最小限に抑えることが大切です。
キジバト猟を楽しむために
キジバト猟は、比較的気軽に始められる狩猟の一つですが、鳥獣保護管理法や地域の条例を遵守し、安全に配慮しながら行うことが大前提です。
他のハンターや一般の通行人、民家などに十分注意し、適切な場所でマナーを守って猟を行うことで、豊かな自然の恵みに感謝し、その醍醐味を味わうことができるでしょう。
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。




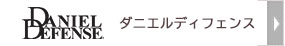





















コメントを残す