
「狩猟に使えるナイフが欲しいけど、何を選べばいいのか分からない。」そんな悩みを抱える方におすすめなのが、スウェーデン発の実用ナイフブランド「モーラナイフ」です。
手頃な価格ながら、解体や皮剥ぎに十分対応できる切れ味と耐久性を持ち、狩猟現場でも信頼されています。
この記事では、モーラナイフの基本スペックや代表モデルの違い、狩猟での活用術、メンテナンス方法まで詳しく解説します。
モーラナイフとは?狩猟者が知っておきたい基本知識
モーラナイフは、狩猟を始めたばかりの初心者から、実用性を重視する中級者まで、幅広い層に支持されているナイフです。
手頃な価格ながら、解体や皮剥ぎに必要な性能をしっかり備えており、「まずは一本試してみたい」「高価なナイフはまだ不安」という方に最適です。
まずは、モーラナイフの基本的な特徴やブランドの背景、狩猟に使える理由をわかりやすく解説します。ナイフ選びに迷っている方は、まずここから知識を深めてみましょう。
スウェーデン発の高コスパナイフブランド
モーラナイフ(Morakniv)は、スウェーデンの刃物の街モーラで製造される伝統的なベルトナイフです。シンプルで丈夫な構造と、圧倒的なコストパフォーマンスが特徴です。
モーラナイフの特徴
モーラナイフの特徴として、以下のものが挙げられます。
- スカンジグラインによる高い切断力
- 握りやすいラバーグリップ
- 軽量で持ち運びやすい
- 価格は1,500〜7,000円程度と手頃
狩猟用途に使える理由
モーラナイフが狩猟に適している最大の理由は、解体や皮剥ぎに必要な刃厚・刃長・操作性をバランスよく備えている点にあります。
特に鹿や猪などの中〜大型獣の解体では、関節を外す、皮を剥ぐ、内臓を傷つけずに切り分けるといった繊細な作業が求められます。
モーラナイフの多くのモデルは、刃先が細く、スカンジグラインドによる鋭い切れ味を持ち、こうした作業に非常に適しています。
また、軽量で取り回しがしやすいため、長時間の作業でも手が疲れにくく、狩猟現場でのサブナイフとしても重宝されます。
たとえば、大型のフルタングナイフや鉈で大まかな処理を行い、細部の仕上げや皮剥ぎにはモーラナイフを使うという使い分けが一般的です。
狩猟に適したモーラナイフの種類と選び方

モーラナイフにも色々な種類があります。ここでは狩猟用途に向いた代表モデル(Companion、Garberg、Kansbol)を比較しながら、刃厚・素材・使い方の違いをわかりやすく解説します。
Companion(コンパニオン)

Companionは、モーラナイフの中でも幅広い用途に使用できる定番モデルです。アウトドアやフィッシングの時や狩猟の場合は解体時の関節外しや皮剥ぎといった繊細な作業に十分な強度と切れ味を発揮します。
スカンジグラインドの刃付けにより、肉や皮にスッと入り込む鋭さがあり、初心者でも扱いやすいのが特徴です。
グリップはラバー素材で滑りにくく、血や脂で手が濡れていても安定した操作が可能。軽量で取り回しが良く、長時間の作業でも疲れにくいため、サブナイフとしてだけでなく、メインナイフとしても十分に活躍します。
Garberg(ガーバーグ)

Garbergは、モーラナイフの中でも最もタフな構造を持つ本格派モデルです。最大の特徴は、フルタング構造で刃がグリップの端まで一体化していることで、強い力を加えても破損しにくく、過酷な環境下でも安定した作業が可能です。
解体作業はもちろん、骨の周りを攻めるような力のかかる処理や、枝払い・薪割りなどのハードな用途にも対応できるため、メインナイフとして一本で完結したい狩猟者に最適です。
グリップはラバー素材で握りやすく、濡れた手でも滑りにくい設計。シース(ナイフケース)は頑丈なポリマー製またはレザータイプが選べ、ベルトやバックパックにしっかり固定できる携行性も魅力です。
モーラナイフ ガーバーグ ブラックブレード スタンダード(C)
モーラナイフ ガーバーグ ブラックブレード STD(C) ダーラレッドエディション
Kansbol(カンスボル)

Kansbolは、モーラナイフの中で狩猟に特化したモデル位置付けとしてラインナップされており、人気があります。刃先は細かい作業に適した形状で、皮剥ぎや内臓処理などの繊細な作業に向いています。
「細かさと強さの両立」により、Kansbolは狩猟現場でのサブナイフとしてはもちろん、キャンプやブッシュクラフトとの兼用にも非常に適しています。軽量で持ち運びやすく、バックパックやベルトに装着しても負担にならないため、長時間の山行や複数日の猟でも快適に使えます。
狩猟とアウトドアを両立したい方にとって、Kansbolは軽快さ・実用性・安心感を兼ね備えた一本として、頼れる相棒になります。
気になる方は、まずはどんなナイフがあるか見てみるのもおすすめです。リンク先からモーラナイフの商品一覧をご覧いただけます。
モーラナイフ商品カテゴリ一覧ステンレス vs カーボンスチール
ナイフの素材選びは、使い勝手やメンテナンス性に大きく関わります。狩猟用途でよく使われる「ステンレス」と「カーボンスチール」には、それぞれにメリットと注意点があります。
ステンレススチール
- 錆に強く、メンテナンスが楽
- 血や水分が付着してもサッと洗える
- 雨天や湿地でも安心して使える
- 初心者やメンテナンス頻度を減らしたい人におすすめ
カーボンスチール
- 切れ味が鋭く、細かい作業に向いている
- 研ぎやすく、現場での再調整がしやすい
- モーラではブラックコーティングされているモデルもあり、見た目のカッコよさもあり。(研ぐとコーティングは落ちます)
- 定期的な手入れができる人、切れ味を重視する人におすすめ
どちらを選ぶかは、使用環境・メンテナンスの手間・求める性能によって変わります。
「濡れやすい環境で気軽に使いたい」ならステンレス、「切れ味と育てる楽しさを重視したい」ならカーボンが向いています。
狩猟スタイルに合った素材を選ぶことで、ナイフの性能を最大限に引き出すことができます。
モーラナイフのメンテナンスとカスタム方法

モーラナイフは、価格以上の性能を持つ実用ナイフですが、長く使うためには定期的なメンテナンスとちょっとした工夫が欠かせません。
特にカーボンスチール製のモデルは、錆対策や刃の手入れをすることで、性能を維持しながら“自分だけの一本”に育てることができます。
ここでは、メンテナンスとカスタム方法を解説していきます。
黒錆加工でカーボン刃を長持ちさせる
カーボンスチール製のモーラナイフは、切れ味に優れる一方で水分や血液に触れると錆びやすいという弱点があります。そこで有効なのが「黒錆加工」。これは、刃の表面に安定した酸化皮膜(黒錆)を作ることで、赤錆の発生を防ぎ、刃を長持ちさせる処理方法です。
家庭でも手軽にできる方法として、酢や紅茶を使った黒錆処理があります。刃を脱脂したあと、酢や濃い紅茶に数時間浸けることで、黒錆が形成されます。処理後は水洗いし、乾燥させたうえでオイルを塗布すれば完了。見た目も渋くなり、“自分だけの一本”として育てる楽しさも味わえます。
※こちらの黒錆加工はモーラナイフ公式が「推奨」しているわけではありませんが、カーボンモデルを狩猟で使うユーザーにとっては、実用性と安心感を高める有効な手段です。特に北海道のような湿度や血液の付着が多い環境にとっては、適切なメンテナンス術と言えます。
研ぎ方・砥石の選び方と頻度
モーラナイフの多くは「スカンジグラインド」という刃付けがされており、初心者でも研ぎやすい構造になっています。刃の角度が一定で、砥石にしっかり当てやすいため、研ぎの失敗が少なく、切れ味の回復もスムーズです。
使用頻度にもよりますが、狩猟やキャンプで数回使用したら、軽く研いでおくことで刃の寿命が延びます。より鋭い切れ味を求める場合は、仕上げ砥を使うと、皮剥ぎなどの繊細な作業がより快適になります。
また、現場での応急処置には、ポケットサイズのダイヤモンドシャープナーが便利です。軽量で持ち運びやすく、ちょっとした刃こぼれにも対応できます。
モーラナイフを選ぶ際の注意点と限界
モーラナイフの一部モデル(Companionなど)はフルタング構造ではないため、強い力を加える用途には不向きです。薪割りや骨を断つような作業では、刃が折れるリスクもあるため、用途を見極めて使うことが重要です。
また、カーボンスチール製は錆びやすいため、黒錆加工やオイル塗布などのメンテナンスが必要です。手入れを怠ると性能が落ちるため、「育てる道具」として付き合う意識がある方に向いています。
モーラナイフは、「狩猟を始めたい」「まずは実用的な一本が欲しい」と考える方にとって、価格・性能・扱いやすさのバランスが非常に優れた選択肢です。使い方や目的に合わせてモデルを選べば、現場でしっかり活躍してくれる頼れる相棒になります。
まとめ
モーラナイフは、狩猟に必要な性能を備えながら、価格以上の実用性を発揮する優秀なナイフです。CompanionやGarbergなどのモデルを理解し、自分の狩猟スタイルに合った一本を選ぶことで、現場での作業効率と安全性が向上します。
さらに、使い込むほどに手に馴染む「育てる道具」としての楽しさもあり、狩猟の相棒として長く付き合える一本になります。
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。



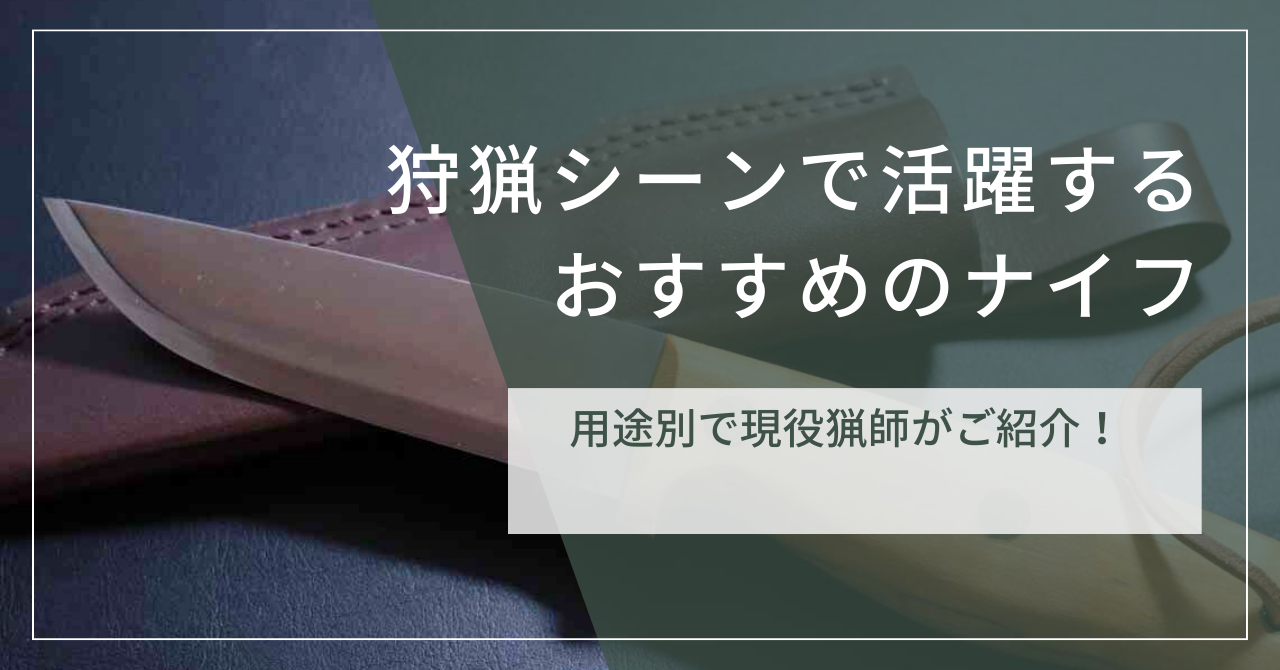




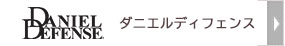





















コメントを残す